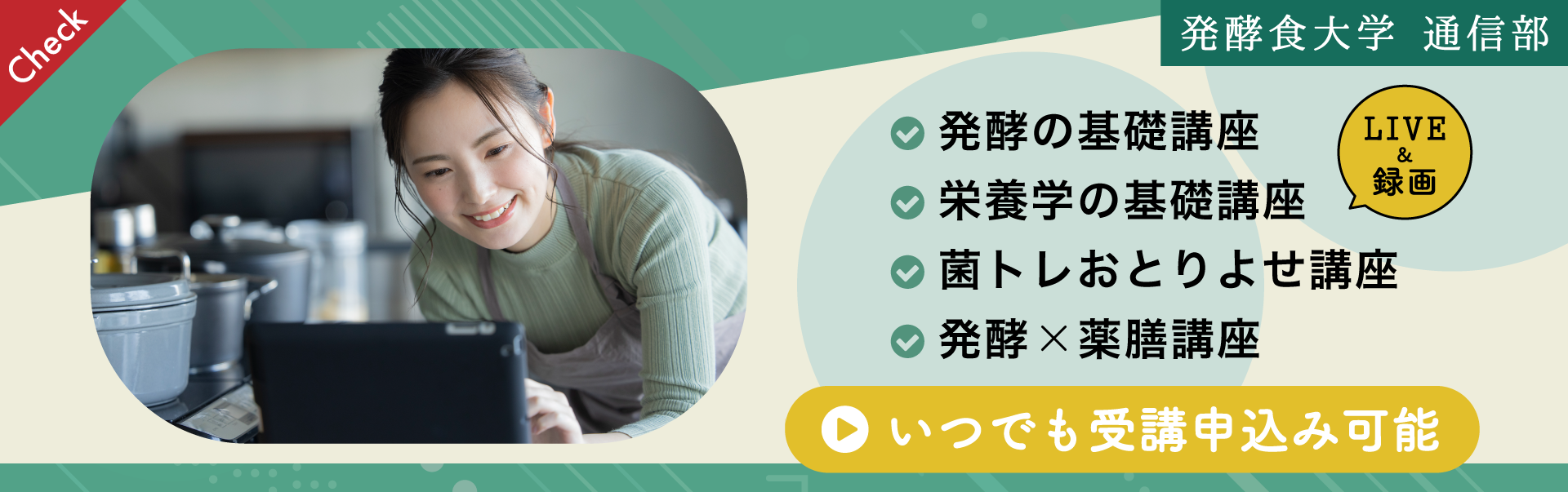前回の甘酒ティスティングをふまえて、みなさん手作りの甘酒を持ち寄る日。
小紺先生の審査で、甘酒グランプリを決定します!
先生の味見に、みなさんドキドキハラハラの様子。

前回、「優勝を目指します!」と宣言した学生さんは、普通米、発芽玄米、イタリア米、古代米のなんと、4種を提出。
小紺先生は「イタリア米がさらりとした風味で新鮮な味わい」と絶賛しておられました。

みなさん、さまざまな糀、お米を使ってチャレンジ。
材料はもちろん、醸し方、その場所に居付く菌によって味わいが変わってくるのが、甘酒作りの面白さです。

いよいよ、審査発表☆
本日の甘酒グランプリはこのお二方!おめでとうございます~
4種の甘酒で挑んだ方、もち米でコクのある味を育んだ方が見事に選ばれました。
先生のお墨付きを得た甘酒にはこの後、学生さんたちが味見に殺到。
みなさん熱心にお手本の味を確かめていましたよ!


この後の講義は、「野菜をたっぷり食べるための糀調味料の活用」がテーマです。
肉食に偏りがちな現代の食生活では、腸内に悪玉菌が増えすぎてしまいがち。
小紺先生によれば、「動物性食品の約3倍量の野菜や発酵食の摂取が必要」なのだとか。

「野菜が多めの食生活では味気ないのでは」との心配は無用。
発酵調味料を活用することで、コクや甘みが増し、素材本来の旨味を引き出してくれる、と小紺先生は語ります。

さぁ、では実際に野菜たっぷりの献立を作ってみましょう!
今回はいつにも増して、野菜が盛りだくさん!
それぞれの素材の持ち味を融合するのが発酵調味料です。

<調理実習メニュー>
- ベジバーグ
- 緑の糀ソースのラップサラダ
- 赤レンズ豆とキャベツの塩粕汁
- 甘酒バナナマフィン

美味しく手早く料理する方法を学ぶ調理デモ。
しっかりメモを取る学生さんに本気度を感じます!

調理台の上のミラーで先生の手元もよく見えますね♪

肉が入らないベジバーグはまとまりにくいのが難点。
そのために、じゃがいものすりおろしをつなぎに使います。
やわらかい食感を出すために、焼き麸を入れるのも特徴です。

ラップサラダに使う<緑の糀ソース>はジェノペーゼソース風。
ここではバジルの替わりに、大葉を使います。
香りも風味も抜群のこのソース。
野菜のディップやパスタにも利用できますよ。

調理実習では、発酵食大学院のOGがアシスタントとして大活躍!
手順から切り方まで詳しく指導してくれました♪


どれも手軽なメニューなのでサクサク仕上がります。
焼き上げ30分のバナナマフィンができたら、調理は完成!
甘酒スイーツはしっかりと熱を通すことで味わいが増します。
こんがり焼けたマフィン、美味しそうです~(^^♪

では、班ごとにテーブルについて、いただきま~す!
野菜中心の本日のメニューは量がたっぷりに見えても、胃腸への負担は少ないですよ。

<本日の参加者VOICE>
- 美味しくしようと一生懸命に甘酒を作ってきました。今回は先生の講評をお聞きできたり、ほかの人の甘酒も味見できたりと、勉強になりました。
- 発酵食を実践するようになって以来、自然と野菜中心のメニューになっていたのですが、夫や子供からは肉コールが多かったんです(笑)。今回のベジメニューは肉が入っていなくても十分満足できるし、喜んでもらえそうです。
- 甘酒選手権には真剣に取り組みました。認めていただいてうれしかったです。本日のレシピは家庭菜園で作っている野菜を大いに活かせそうです。

- 前回に引き続き、「甘酒は糀などの素材で大きく味が変わってくるんだなぁ」と実感しました。地元の糀を使って、さらに美味しい甘酒を作っていきたいです。
- 今日のマフィンは本当に美味しかったです。砂糖を使わなくてもこんなに味わい深いスイーツが作れることに感動しました。
甘酒を仕込み、使い、みなさんその魅力にハマっているようですね☆
次回の教室の会場は「金城納豆」さん。
納豆の製造のヒミツや食べ比べなど、納豆好きにはたまらない内容です。どうぞ、お楽しみに♪